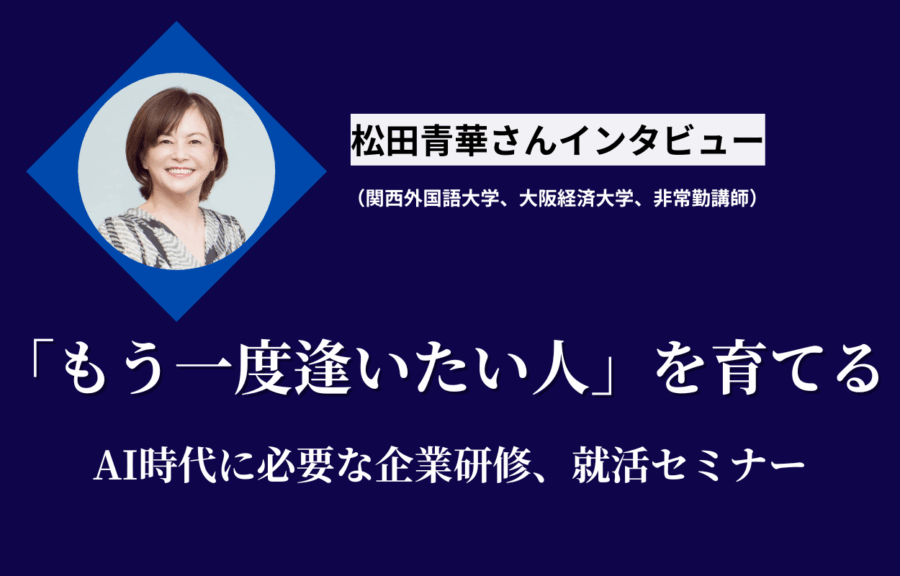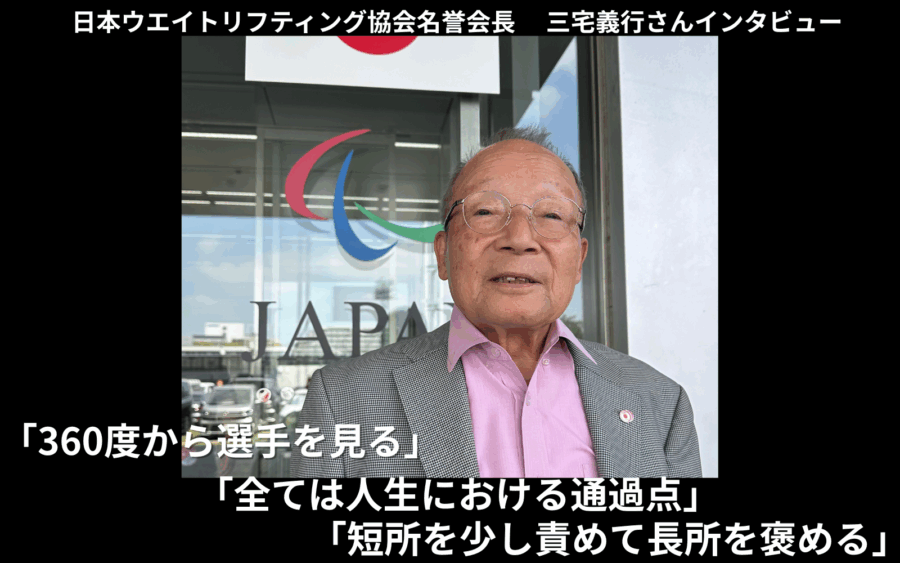李 忠成の生き様「自分より上手い相手に勝つ」方法
酒を飲みながら見たW杯~神様でも消せないゴール

李忠成の言葉を聞いて欲しい。
純粋にそう思えるようなインタビューだった。
株式会社SUNLOGUEの創設にあたり、知人を通じて最初に講師として了承をしてくれたのが彼だった。
新聞記者時代、15年ほどサッカー担当をしていたが、関西中心の取材活動だったこともあり、現役時代を取材した記憶はない。
それでも彼はこう言って、ゼロからスタートする名もない会社の取材に応じてくれた。
「自分の生き方を参考にして欲しい」
私がこの記事をしたためることに、何の意味があるのだろう。
おそらく文字だけでは、彼の生き様の半分も伝えることはできない。
在日韓国人として生まれ、帰化してからも、自分が何者であるかを探し続けてきたのではないだろうか。
もがき、苦しみながら、自らの力でアイデンティティーを見つけたのだ。
それは、1本のゴールだった。
2011年1月29日、日本代表として出場したアジアカップ決勝戦。
延長後半にオーストラリアのネットを豪快に揺らしたボレーシュートは、日本を優勝へと導く劇的なゴールになった。
「人生を変えました。
李忠成といえば、サウサンプトンでも、浦和のルヴァンカップ(決勝)で決めたゴールでもなく、あのボレーシュート。100人に聞いたら99人が〝あのゴール〟という代名詞ができた。
ゴールという結果は、神様でも、消しゴムでも消せない」

(サンフレッチェ広島時代=所属事務所提供)
その前年にあったワールドカップ南アフリカ大会。
岡田武史監督が率い、本田圭佑や松井大輔、大久保嘉人らが躍動し、自国開催以外のW杯で日本が初めて16強入りした大会は、遥か遠くの出来事のようだったという。
当時はサンフレッチェ広島に所属。2008年北京五輪を一緒に戦った本田や長友佑都らが快進撃を続ける姿を、酒を飲みながら見ていた。
「俺は何をしているんだろう」ー
心の奥底に眠っていたものに気づいたのは、その時だった。
「心の檻の中に100匹の羊がいる。そこに1匹でもオオカミがいると羊は食べられてしまう。1日だけなら休んでもいいだろう。そう考えるのがオオカミで、自分に言い訳を作った瞬間に心が食われてしまう。言い訳はできないようにしないといけないんです。
例えば、毎日10回シュートをやろうと決めたからには、やり続ける。今日は疲れているからと、9回で終わりにしてはダメ。勝負の神様は細部に宿る。そう思い続けて、純粋に100%の努力を続けてきた人にしか結果は生まれない」
誇れない自分、1年目に告げた「もう辞めます」
自分だけの人生ではなかった。
その背中に、多くのものを背負っている。
2007年に日本国籍を取得すると、北京五輪の救世主として大きな注目を浴びた。
「スポーツ新聞はほぼ全紙『李忠成帰化』を1面で伝えていました。それまでは(練習場に)サンダル、パジャマみたいな格好で行っていた自分が、ちゃんとした服装をしないといけないと思いました。
後ろには『在日韓国人』『在日朝鮮人』という『在日』の人たちが付いてくる。僕が乱暴な言葉で『ぶっ殺す』と口にしてしまえば、なんであんなヤツの帰化を許したんだ、と思われる。僕はみんなを背負っている。絶対に『LEE』としてオリンピックに出て、在日韓国人の道を作りたかった」
自分を、誇れない時期もあった。
李忠成とは、最初から今の「李忠成」ではなかったのだ。
FC東京のU-18(ユース)からトップチームに昇格したプロ1年目。
公式戦で出場機会はなく、居場所を見つけられずにいた。
どこに進んだらいいのだろう。夢や目標まで見失った。
「1年目は活躍できなかったです。誰にも頼られなくなって、人って、そういう時に何をするか?って。頼られたいから、媚びを売るようになるんです。パシリをするようになっていました。
『先輩、送りますよ!』とか。アッシーになって、イジメにも近いようなパシリだった。人って、そんなもんですよ。人の欲求を探して、媚びを売っていた時期が、人生で1番きつかった」
プロ1年目のシーズンが終わると、当時、FC東京の強化部長を務めていた鈴木徳彦氏にこう伝えたのだという。
「もう僕は辞めます」
複数年契約だったが、2年目を迎える書類にサインをしなかった。
「事実上の契約破棄でした。こういう人生を送るために、サッカーをしているんじゃない」
大学に入って、1からやり直すつもりだった。
そんな時に彼を拾ってくれたのが、同じJ1の柏レイソルだった。
わずか1年でFC東京を退団。それは、まだ結果を残していないルーキーにとって、異例のことでもあった。
「環境が変われば、人は変われるんじゃないか? そう思っていました」

(柏レイソル時代=所属事務所提供)
人は「1つ自信がつけば変われる」
彼にはいくつかの分岐点がある。
インタビューを通じて感じたのは、どん底にいたとしても、そこから再び這い上がろうと必死にもがき、より高い山へと登っていく姿だった。
それが李忠成を、李忠成として成長させた理由ではないだろうか。
「こんな自分でも、1つ自信がつけば変われるんです」
彼はそう言った。
ただ、人生を変えることができるのは、変わろうとする人だけだ。
彼はそのヒントをくれる。
「本を読んでも分からない。YouTubeで見るものでもないんです。サッカーに限らず、人をロールモデルにすることで、成功の物差しを身につけて欲しい」
投資会社を設立する傍ら、47都道府県をまわってサッカー教室を開いている。
「プロと同じシュートスピード、ジャンプを生で見ることで、それが指標になる」
最初から自信があったわけではない。
むしろ、あのまま消えてしまっても、おかしくはない瞬間は何度かあった。
プロ1年目、そして酒場でW杯を眺めていた2010年。
「基本、自分は能力がないんです。
めちゃくちゃ足が速いわけでもない、背が高いわけでもない。
だからこそ、どうやって(相手に)勝つか、それを考えたんです。
長友(佑都)が50メートルを5秒8で走るとする。
僕は6秒0。
その差はめちゃくちゃ速いように見えるけど、僕が長友より0.3秒前にスタートすれば勝てるわけです。僕は0.3秒早く走り始めて、勝つ方法を考えた。
だから、自分よりも上手い選手に勝つこともできたんです」

(横浜Fマリノス時代=所属事務所提供)
言葉とは、不思議な力を宿している。
その言葉を発することで、自分が進む道が見えることがある。
そして、覚悟が芽生える。
あのゴールを、覚えている。
今から10年以上も前の出来事なのに、鮮明に記憶に刻まれている。
彼は帰化をして日本人になった。
そのゴールは彼の生き方の縮図であり、これからグローバルな世界が始まるんだということを教えてくれるゴールでもあった。